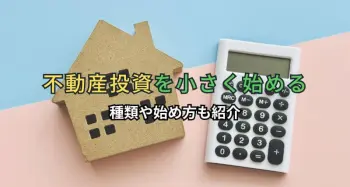
投資マンション基礎知識
不動産投資の地震リスクとは?賃貸経営で知っておくべき対策と備え
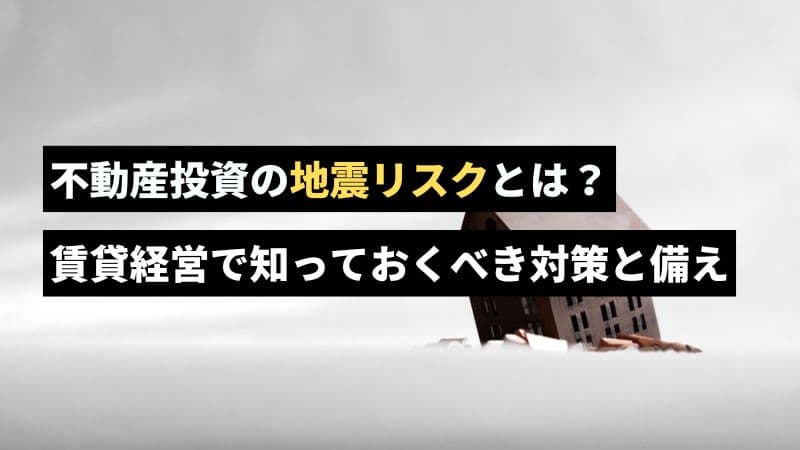
不動産投資では安定した収益が期待できますが、地震という自然災害のリスクは避けられません。大きな地震によって建物が損壊すると、修繕費の増加や資産価値の低下、さらには空室率の上昇といった事態が考えられます。
投資した物件を守りながら収益を維持するには、地震リスクを正しく理解し、適切な対策を行うことが不可欠です。そのため、今後の地震発生率や投資リスクを理解し、回避するための対策について理解しておきましょう。
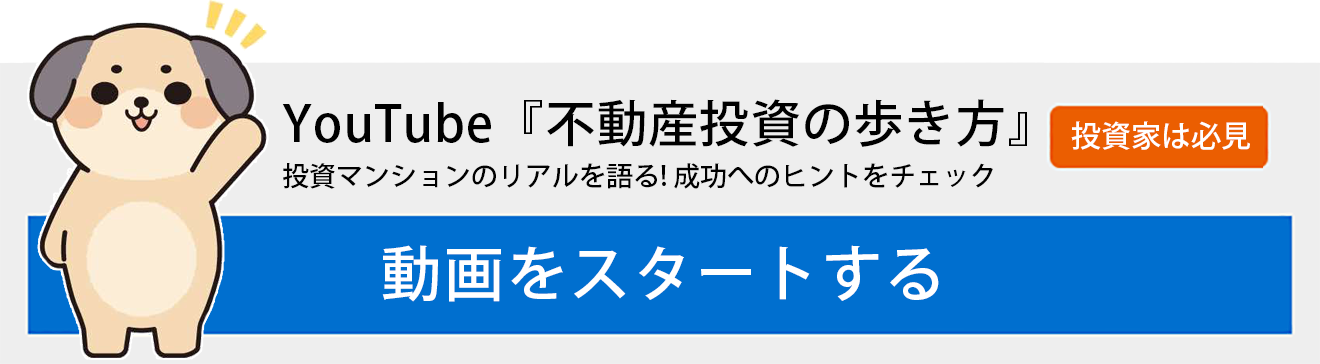
目次
日本で大地震が発生する確率と被害予想
日本で不動産投資を行う以上、地震リスクは無視できません。地震による被害を少しでも抑えるためには、地震による不動産投資への影響、対策について知っておく必要があります。この章では、今後日本で大地震が発生する確率と被害予想について解説します。
30年以内に大地震が発生する確率
内閣府が運営する「防災情報のページ」によると、30年以内に大地震が発生する確率は以下の通りです。
| 地震の種類 | 30年以内に大地震が発生する確率 | 根拠となる情報 |
|---|---|---|
| 海溝型地震(宮城県沖の場合) |
|
|
| 活断層による地震(静岡構造線断層帯の場合) |
|
|
出典:内閣府「特集 地震を知って地震に備える! : 防災情報のページ」
特に注意するべきは海溝型地震です。30年以内に大地震が起きる可能性が高く、島国である日本ではどのエリアにおいても、海溝型地震のリスクを抱えているといえるでしょう。
首都直下型地震が発生した場合の影響
同じく内閣府の「防災情報のページ」で、首都直下地震の被害想定と対策についても解説されています。同ページによると、首都直下地震による被害想定は以下の通りです。
| 地震の揺れによる被害 |
|
|---|---|
| 市街地火災の多発と延焼 | 【焼失】
【死者】
|
また、地震対策の方向性として「M7クラスの地震はどこが震源となるかはわからないため、首都圏全般での耐震化を推進する」と明記されています。
首都直下地震により建物が受けるダメージは非常に大きいと予想されており、国も耐震化の推進を掲げています。以上のことから、高い耐震性は日本の不動産に必須の要素といえるでしょう。
参考:内閣府「特集 首都直下地震の被害想定と対策について(最終報告)‐内閣府防災情報のページ」
- 投資マンション相場検索 高値売却はこちら
- 0120-109-998
-
10:00~19:00((年末年始除く))

地震が起きたときの不動産投資リスク
前章では、日本で大地震が発生する確率および被害予想について紹介しました。大地震が起こる確率は決して低いといえず、発生した場合は甚大な被害は避けられないでしょう。
この章では地震が起きたときの不動産投資リスクを紹介します。
賃貸物件の損壊による資産価値の低下
地震により建物が倒壊しなかった場合でも、以下のような被害が起こる可能性があります。
- 外壁にヒビやキズが入る
- タイルや壁材の一部が剥がれる
- 電球など照明の部品が落下する
- 建物の基礎部分や設備に損傷が起こる
資産価値の下落によって当初の家賃が市場相場より高いと判断されると、入居希望者がなかなか集まらず、管理会社からも値下げを提案されることがあります。また、既存の入居者が民法611条に基づき減額を請求されるケースもあるため、賃料の引き下げを検討せざるを得なくなるかもしれません。
また、建物の修繕が不十分なまま放置していると資産価値は低下したままとなり、売却価格が低くなる恐れや買い手がなかなか見つからない可能性も高いのです。
修繕費用などの支出の増加
地震により建物が損壊した場合、修繕費用などの支出が大幅に増加する恐れもあります。地震保険に加入していれば保険金が支払われるとはいえ、修繕費用の全額をカバーできるとは限りません。
保険金を超える部分は自己資金から修繕費の支出が必要です。
入居者のケガ・死亡による損害賠償
地震のような自然災害は不可抗力のため、地震が原因で入居者のケガ・死亡が起きても原則として損害賠償責任は負いません。
しかし、建物に瑕疵があった場合は、オーナーに責任を問われる恐れがあります。オーナーが賠償責任を負うケースとして以下の例が挙げられます。
- 建築当時の耐震基準を満たしていない
- 現状の建築基準法に違反している
- 建物の老朽化を放置していた、十分な修繕を行っていなかった
建物の管理状況によっては、多額の賠償を負う事態が起こり得る点にも注意が必要でしょう。
空室率の上昇
地震による影響を受けるのは発生の直後だけとは限りません。地震によって建物が損壊した、オーナーや管理会社の対応に不満があったなどの理由から、退去が発生する恐れもあります。
また、地震によって建物が損壊し、修繕が完了するまで新たな入居者を迎えられない状態になるケースもあるでしょう。以上のように、地震を機に空室率が上がり、家賃収入が下がるリスクもあることがわかります。
賃料の引き下げによる収入ダウン
地震が原因で賃料を下げる必要が生じ、家賃収入が下がる恐れもあります。賃料の引き下げが必要になる主な理由は以下の2つです。
- 損壊により資産価値が下がり、元の家賃では高すぎる状態になる
- 地震を機に周辺の競合物件が家賃の引き下げを実施したため、相場に合わせる必要性が生じる
入居率が変わらなくても、家賃の引き下げを行えば家賃収入は少なくなってしまいます。
マンション投資に関するお問い合わせはこちら
- 投資マンション相場検索 高値売却はこちら
- 0120-109-998
-
10:00~19:00((年末年始除く))

地震による不動産投資リスクの回避策
地震による不動産投資のリスクを最小限に抑えるためには事前の対策が必須です。この章では、リスクを抑える効果が期待できる方法を3つご紹介します。
物件の耐震性を確認する
最初に行うべきなのが物件の耐震性を確認することです。地震による影響が小さければ、前章で紹介したリスクの懸念も少なくなります。そして、地震による影響の程度は物件の耐震性によって大きく左右されます。
つまり、地震による不動産投資のリスクを抑えるためには、耐震性の高い物件で賃貸経営を行う必要があるのです。
1981年6月に改正された新耐震基準は、震度6強〜7程度の大地震でも倒壊・崩壊しにくいとされています。これから不動産投資を始めるのであれば、新耐震基準を満たしている物件を選びましょう。
既に不動産投資を実施している方であれば、なるべく早く耐震性を確認する必要があります。法律上は建築当時に運用されていた耐震基準を満たせば問題ありませんが、地震のリスク回避を考えると、新耐震基準を満たすのが理想です。
賃貸物件の耐震性に不安がある場合は、耐震工事も視野に入れるべきでしょう。
参考:国土交通省「建築:住宅・建築物の耐震化について」
投資する物件のエリアを分散させる
複数の物件で不動産投資を行う場合、災害リスクを抑えるために投資する物件のエリアを分散させるのが理想です。
たとえば、Aというエリアにある物件が地震による被害を受けても、Bというエリアの物件は通常通り経営を続けられるため、収入減少を最小限に抑えられます。
ただし、遠方の物件は様子を直接確認するのが難しいため、トラブルに気付くのが遅れる可能性があります。リスク分散を目的に遠方の物件で不動産投資を行うのであれば、遠方ならではの対策が必須です。
信頼できる管理会社を選ぶのはもちろん、小まめな報告も依頼すべきといえます。
費用対効果を考えて売却や買取を検討する
物件の耐震性に不安がある場合や、地震によるリスクが高いと考えられる場合、物件を手放すのも1つの手段です。
不動産投資で注意するべき事項の1つとして、物件を地震で失ってもローン返済は残る点が挙げられます。不動産投資ローンはあくまでも物件を購入するためのお金を貸し付ける制度であり、物件の維持を保証するサービスではありません。
お金を借りている以上、建物の状態を問わずローンの返済義務は残ります。倒壊まではいかずとも、地震によって資産価値の下落や家賃の引き下げの必要性が生じる恐れはあります。前章で説明した通り、修繕費や損害賠償など様々な支出が発生する可能性も高いのです。
不動産を手放せば地震による不動産投資のリスクは必ず回避できます。とはいえ、家賃収入がなくなる、すなわち収入源が1つ減ることは大きなリスクといえるでしょう。不動産の売却や買取を検討する際は、費用対効果を十分に検討する必要があります。
あなたのマンション・アパートの価格が分かる
コラム監修

伊藤 幸弘(いとう ゆきひろ)
株式会社TOCHU(トウチュウ)代表取締役
投資マンション専門家/不動産コンサルタント
プロフィール
2002年より投資用中古ワンルームマンション売買のキャリアをスタートし、現場での売主・買主双方のリアルな課題解決を通じて、個人投資家の資産形成支援に従事。
2014年に株式会社東・仲(現:株式会社TOCHU)を立ち上げ、通算の取扱実績は20,000件以上。
2025年からは業界初の価格透明化サービス「TOCHU iBuyer」を展開し、中古投資マンション市場の健全化を推進。
「誠実な取引こそが市場の信頼をつくる」という理念のもと、投資マンションの適正な価値形成を目指して活動している。
保有資格
・公認 不動産コンサルティングマスター
・宅地建物取引士
・ファイナンシャル・プランニング技能士
・賃貸不動産経営管理士
・投資不動産取引士
・競売不動産取扱主任者
・日本不動産仲裁機構 認定ADR調停人
著書・実績
『投資ワンルームマンションをはじめて売却する方に必ず読んでほしい成功法則』(クロスメディア・パブリッシング)
『マンション投資IQアップの法則 〜なんとなく投資用マンションを所有している君へ〜』(CHICORA BOOKS)




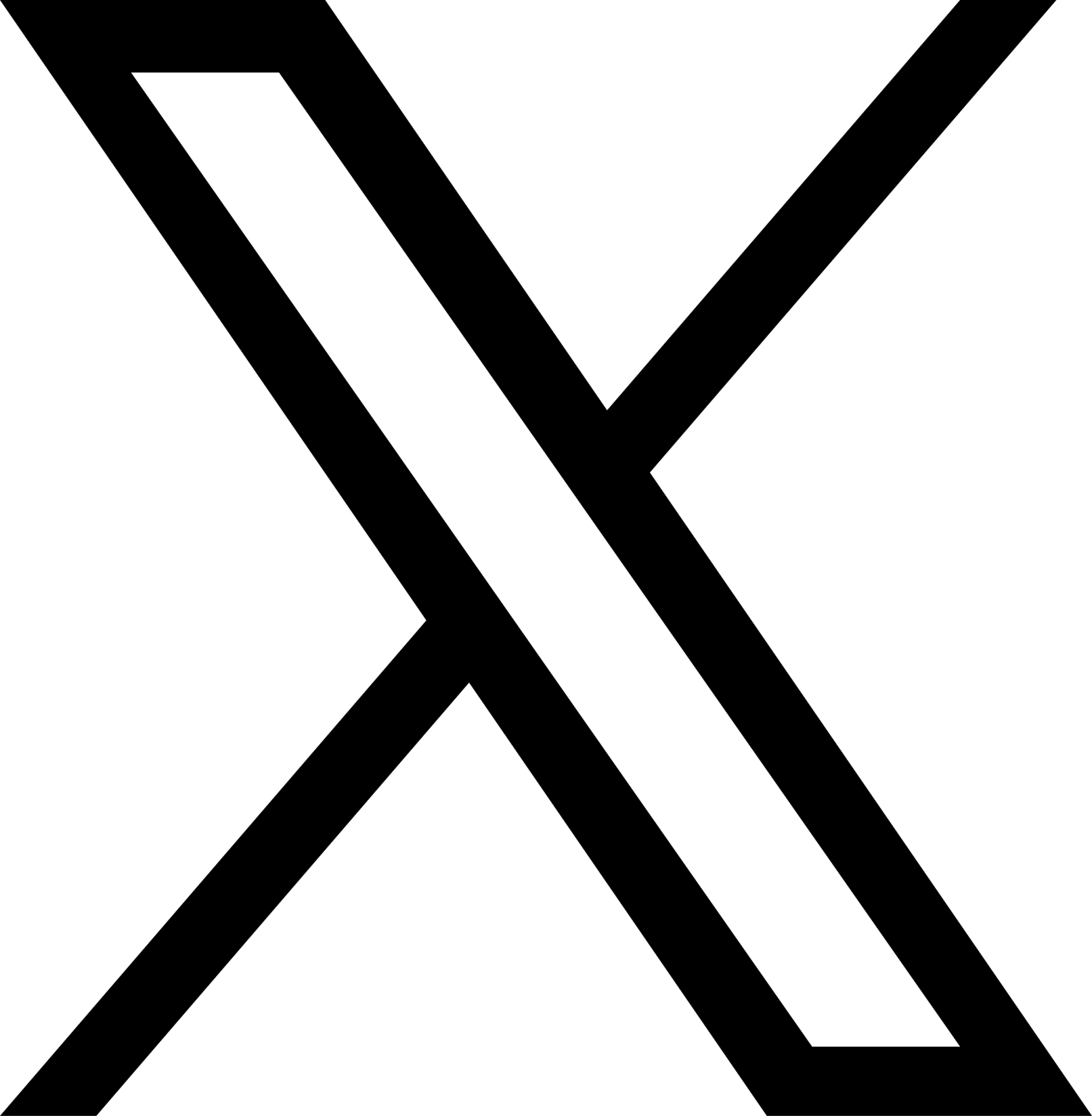
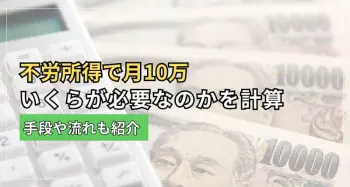
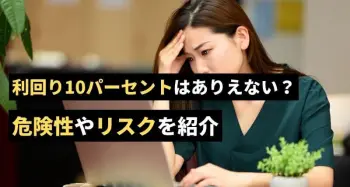
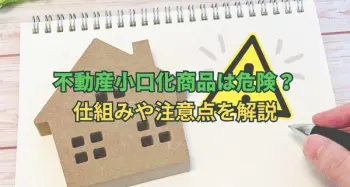
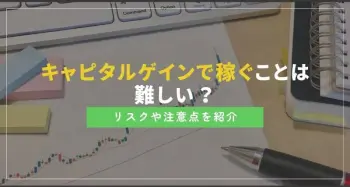
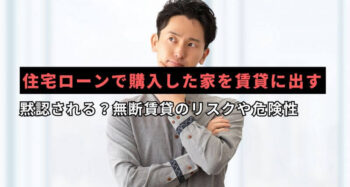
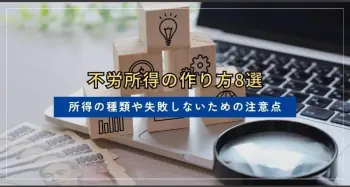

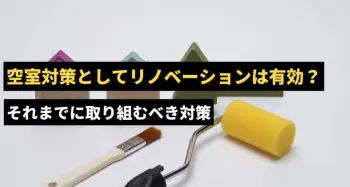
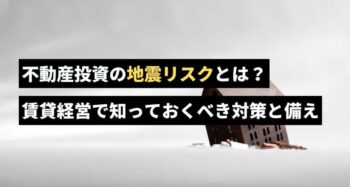

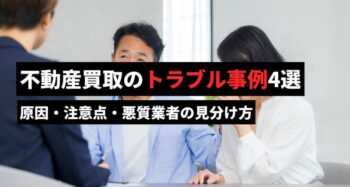
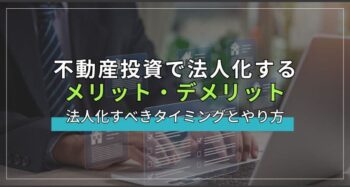
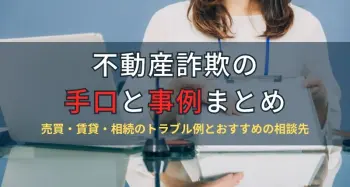
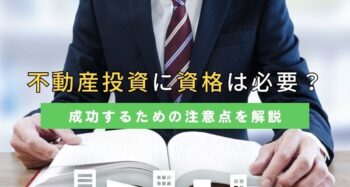
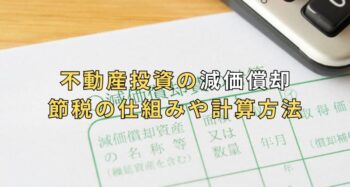
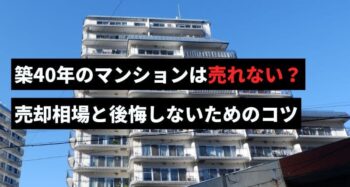
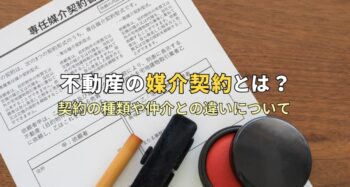
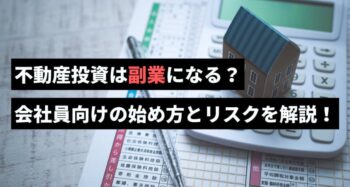
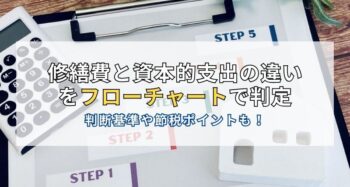
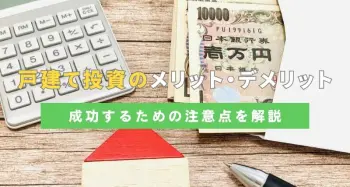
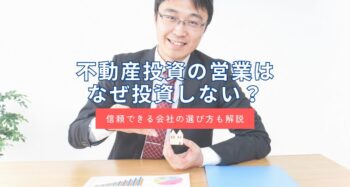
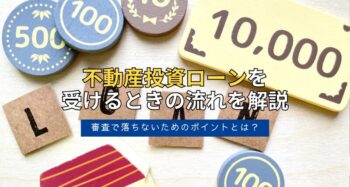
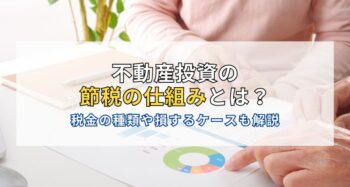

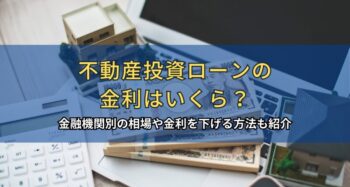
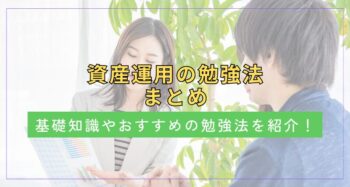




マンション投資に関するお問い合わせはこちら