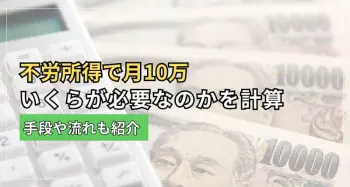
投資マンションオーナに役立つコラム
不動産詐欺の手口と事例まとめ|売買・賃貸・相続のトラブルと相談先を紹介
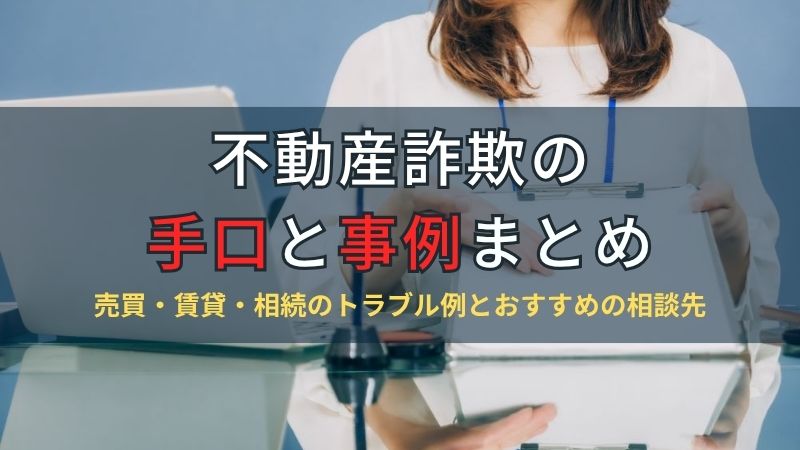
不動産取引では高額な金銭が動くため、詐欺被害に遭う事例が後を絶ちません。
近年では巧妙な手口で大切な財産を狙う業者や、見抜きにくい悪質な勧誘が増加傾向にあります。
こうした被害から身を守り、安全に不動産取引を進めるには、一般的な詐欺の手口と対策の知識が不可欠です。
詐欺被害を防ぐためにも、具体的な手口や事例、信頼できる相談先を把握し、自身と家族の財産を確実に守りましょう。
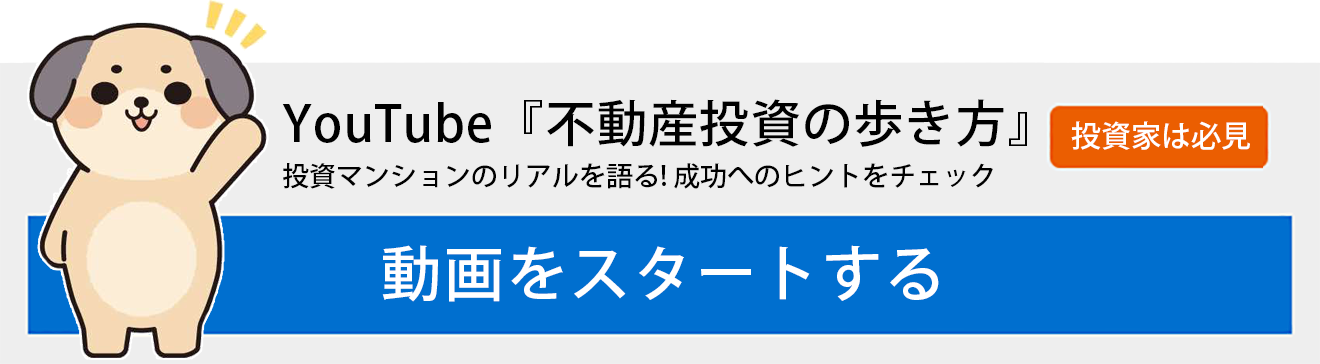
目次
不動産詐欺の主な手口|売買・賃貸・相続・リースバックの事例
不動産取引では、売買や賃貸、相続、そしてリースバックに至るまで、さまざまな場面で詐欺が発生しています。
以下に代表的な手口を紹介しますので、注意すべきポイントをしっかり押さえておきましょう。
地面師による所有者の偽装
不動産詐欺の手口の1つ目は「地面師による所有者の偽装」です。
地面師とは、他人の土地や建物の所有者になりすまし、偽造書類で物件を売却して金銭を騙し取る詐欺集団のことです。
Netflixの「地面師たち」で、地面師の存在を知ったという人も多いのではないでしょうか。地面師による被害を防ぐためには、以下の対策が有効です。
- 不動産登記簿を必ず確認する
- 売主本人と直接面会して身分証を確認する
- 相場より安い価格や現金取引の強要には警戒する
日本では、2017年に大手住宅メーカーが約55億円を騙し取られた事件が有名です。
大きな被害が出る可能性があるため、少しでも「おかしい」と感じたら、自身で判断せずに専門家に相談しましょう。
高齢者を狙った相続詐欺
不動産詐欺の手口の2つ目は「高齢者を狙った相続詐欺」です。
判断能力の低下が見られる高齢者が狙われやすく、相続財産を狙って不正に財産を奪おうとする詐欺が増えています。
相続詐欺のよくある手口は以下の通りです。
- 遺言書の偽造や改ざん
- 「親族」と偽り財産を奪取
- 「相続手続き代行」を装った詐欺業者
大切な資産を守るためにも、家族間で財産状況を共有することが有効な対策法です。
高額なリフォーム契約を強要
不動産詐欺の手口の3つ目は「高額なリフォーム契約の強要」です。
突然の訪問で「無料点検」と称して家に上がり込み、不要な工事を高額で契約させるケースが該当します。
訪問営業によるリフォーム詐欺の手口は、以下の通りです。
- 「点検無料」と称して家を訪問してくる
- 屋根や床下などを点検し、「すぐにリフォームしないと危険」と不安をあおる
- 「今契約すれば特別に割引」と契約を急がせる
- 契約後に高額請求・追加工事の提案
「今なら無料」「今なら割引」など魅力的な謳い文句を言われても、その場では契約しないようにしてください。リフォームの緊急性が高いときでも、複数の業者に見積もりを依頼して内容を比較したうえで判断しましょう。
もしも、不当な内容で契約してしまった場合は、契約書を受け取ってから8日間はクーリング・オフで契約の取り消しが可能です。
クーリング・オフは、宅地建物取引業法や特定商取引法に基づき、一定条件下で利用できます。適用には条件があるため、事前に内容を確認しておきましょう。
サブリース契約の満室保証
不動産詐欺の手口の4つ目は「サブリース契約の満室保証」です。
サブリースとは、物件を所有するオーナーが不動産会社に物件を一括で貸し出し、不動産会社が入居者に又貸し(転貸)する契約方式です。
サブリース契約では、「空室でも家賃収入が安定する」と勧誘されることが多く、特に初心者の投資家がターゲットになりがちです。
しかし、満室保証と謳っておきながら、以下のような可能性があります。
- 契約して数年で家賃が減額される
- 途中で契約を打ち切られる可能性がある
といったトラブルが頻発しています。サブリース契約をする際は、「家賃見直し条項」や「中途解約条件」が契約書に含まれていないか必ず確認してください。
リースバックを利用した詐欺
不動産詐欺の手口の5つ目は「リースバックを利用した詐欺」です。
リースバックとは、自宅を業者に売却した後、同じ家に賃貸契約を結んで住み続けられる仕組みを指します。
急な資金調達が必要な人にとってメリットのある制度ですが、自宅の所有権がなくなるため注意が必要です。「一生住み続けられる」と誤認させるような説明をされたものの、 賃貸借契約によっては契約更新できない場合があります。
また、契約更新時に家賃を大幅に値上げされたり、契約終了後に退去を迫られたりするケースもあるようです。
リースバック契約を結ぶ際は、以下の点に注意しましょう。
- 賃貸契約の期間
- 更新条件
- 家賃改定の有無
「売却しても自宅に住み続けられる」と言われても、所有権がないリーズバックでは必ずしも保証された権利ではありません。不明点があれば契約前に第三者に相談することが重要です。
誇大広告やおとり広告を利用
不動産詐欺の手口の6つ目は「誇大広告やおとり広告を利用する詐欺」です。
「駅徒歩5分で家賃5万円!」「利回り12%保証!」などの誇大広告や、実際には存在しない物件を掲載して客を誘導するおとり広告も詐欺の一種です。
これらはすべて宅建業法で明確に禁止されており、客引き目的の不当な手法とされています。
実際業者に問い合わせても、「その物件はちょうど決まってしまったのですが、別の物件なら紹介できます」と言われて、契約を勧められることが多いようです。
仲介手数料を不当に請求
不動産詐欺の手口の7つ目は「仲介手数料の不当請求」です。
仲介手数料は宅建業法によって、以下の通りルールが決められています。
| 取引 | 上限 |
|---|---|
| 売買 | 3%+6万円(税別) |
| 賃貸 | 家賃1か月分(税別) |
この上限を超えて仲介手数料を請求している業者は、宅建業法違反となります。
契約書に記載のない「事務手数料」や「広告費」が上乗せされていたときは、契約せずに消費生活センターや宅建業指導課などに相談しましょう。
- 投資マンション相場検索 高値売却はこちら
- 0120-109-998
-
10:00~19:00((年末年始除く))

不動産全般でよくある詐欺の事例
不動産詐欺は、誰にでも起こりうる身近な問題です。
ここでは、実際に発生した詐欺の代表的な3つの事例をご紹介し、被害に遭わないための対策も併せて解説します。
投資用マンションの詐欺事例
20〜30代の会社員を狙って将来の家賃収入をアピールしながら、強引な勧誘で高額契約を結ばせる「投資用マンション詐欺」が後を絶ちません。
20代男性は「老後の資産形成に最適」と喫茶店で執拗に説得され、深夜まで帰れない状況の中で2,600万円の契約書にサインを強いられました。契約後に支払いが困難となり、解約を求める相談が多く寄せられています。
対策ポイント
- 高圧的な勧誘はその場で断る、もしくは途中退席する
- 仮に契約した場合は、8日以内ならクーリング・オフ可能
契約書や重要事項説明書に不備がある場合は、宅建業法で違反となる可能性があります。不安な方は、速やかに消費生活センターや弁護士へ相談しましょう。
参考:国民生活センター「20歳代に増える投資用マンションの強引な勧誘に注意!」
認知症の高齢者を狙った詐欺事例
認知症の高齢者が、自覚のないまま不利な不動産契約を結ばされる被害も多く存在します。判断能力の低下を逆手にとる非常に悪質な詐欺です。
実際に、80代の女性が3,500万円で自宅を売却する契約を結ばされ、契約の記録がまったくないまま進行していったケースがあります。
家族が気づいた時には既に解約が難しく、数百万円の違約金を請求されるなど、深刻な事態に発展していました。
高齢者を狙った詐欺被害を防ぐポイントは以下の通りです。
- 成年後見制度の利用で、法的に契約の無効や取消しが可能(状況による)
- 家族が日常的に財産や郵便物をチェックし、異変に早く気づくことが重要
不動産の購入や売却といった大きな金額が動く契約については、第三者の同席や事前相談を徹底しましょう。
リースバックを利用した詐欺事例
「自宅を売ってもそのまま住み続けられます」という言葉を信じ、リースバック契約で住まいを失うケースもあります。
事例として、80代女性が1,000万円で自宅を売却した後、月15万円で賃貸に住む契約をしました。
しかし、収入に見合わない家賃設定だったため、支払いが続かず退去を求められ、住む場所を失いかけたのです。
- 家賃は収入の3割ほどに抑える
- 「一生住み続けられる」といった表現がないか
リースバック契約を結ぶ際は、上記の点を必ず確認しておきましょう。
参考:国民生活センター「強引に勧められる住宅のリースバック契約にご注意!」
マンション投資に関するお問い合わせはこちら
- 投資マンション相場検索 高値売却はこちら
- 0120-109-998
-
10:00~19:00((年末年始除く))

不動産で詐欺に遭ったときにすべきこと
万が一不動産詐欺に遭ってしまった場合でも、適切な対応を取れば被害の拡大や損失の回復ができる場合もあります。
ここでは、被害に気づいた直後にやるべき行動を5つ解説します。
詐欺の証拠をできるだけ集める
まず最優先で行うべきは、詐欺の証拠集めです。詐欺に遭った証拠がなければ、警察や専門機関も十分に動けません。
以下は、集めておきたい証拠の一例です。
- 契約書・領収書・振込明細
- メールやLINEなどのやりとり
- 営業担当との通話録音
- 勧誘内容を記録したメモ
冷静に「誰に、いつ、何をされたのか」が分かるように準備しておきましょう。スマホやPC内のデータは忘れず保存しておいてください。
銀行の口座を凍結する
詐欺被害に遭いお金を振り込んでしまった場合、速やかに振込先の銀行に連絡し、口座の凍結を依頼する必要があります。
| 取るべき行動 | 詳細内容 |
|---|---|
| 銀行へ連絡 | 振込先の金融機関に「詐欺被害である」と連絡 |
| 被害届の提出 | 警察に届け出て、事件番号を控えておく |
| 振込明細の提示 | 取引日時や金額など、具体的な情報を用意する |
「振り込め詐欺救済法」という、犯罪口座の資金が残っていれば、振り込んだお金が返還される制度があります。そのため、詐欺だと気づいたら少しでも早く動くことが重要です。
警察に連絡する
銀行口座の凍結と並行して、警察に通報・相談してください。自分1人では解決できなくても、警察の力を借りることで解決できるかもしれません。
警察への相談には2つの窓口があります。
- 緊急性が高いときは 110番通報
- それ以外は「#9110」の警察相談専用ダイヤル
被害届を提出する際は、あらかじめ証拠を整理しておくとスムーズです。
国民生活センターに連絡する
詐欺被害に遭った場合は、消費生活センターの活用も検討しましょう。
国民生活センターとは、消費生活に関する情報の提供や調査研究、消費者相談・苦情処理、商品テスト、消費者紛争の解決などを行う独立行政法人のことです。
被害内容によっては、クーリング・オフや中途解約ができる可能性もあるため、素早く対応することが重要です。
法テラスに相談する
被害金額が大きい、複雑な契約トラブルが絡む場合は、法テラスを活用して詐欺対応に強い専門家のサポートを受けましょう。
法テラスとは、法的トラブル解決のために国が設立した総合案内所のことです。
法テラスのサポート内容は以下の通りです。
- 法律相談
- 弁護士費用の立て替え
- 法制度に関する情報提供
- 弁護士の紹介
法テラスの相談は基本無料ですので、詐欺被害に遭った場合は利用を検討してみてはいかがでしょうか。
あなたのマンション・アパートの価格が分かる
コラム監修

伊藤 幸弘(いとう ゆきひろ)
株式会社TOCHU(トウチュウ)代表取締役
投資マンション専門家/不動産コンサルタント
プロフィール
2002年より投資用中古ワンルームマンション売買のキャリアをスタートし、現場での売主・買主双方のリアルな課題解決を通じて、個人投資家の資産形成支援に従事。
2014年に株式会社東・仲(現:株式会社TOCHU)を立ち上げ、通算の取扱実績は20,000件以上。
2025年からは業界初の価格透明化サービス「TOCHU iBuyer」を展開し、中古投資マンション市場の健全化を推進。
「誠実な取引こそが市場の信頼をつくる」という理念のもと、投資マンションの適正な価値形成を目指して活動している。
保有資格
・公認 不動産コンサルティングマスター
・宅地建物取引士
・ファイナンシャル・プランニング技能士
・賃貸不動産経営管理士
・投資不動産取引士
・競売不動産取扱主任者
・日本不動産仲裁機構 認定ADR調停人
著書・実績
『投資ワンルームマンションをはじめて売却する方に必ず読んでほしい成功法則』(クロスメディア・パブリッシング)
『マンション投資IQアップの法則 〜なんとなく投資用マンションを所有している君へ〜』(CHICORA BOOKS)




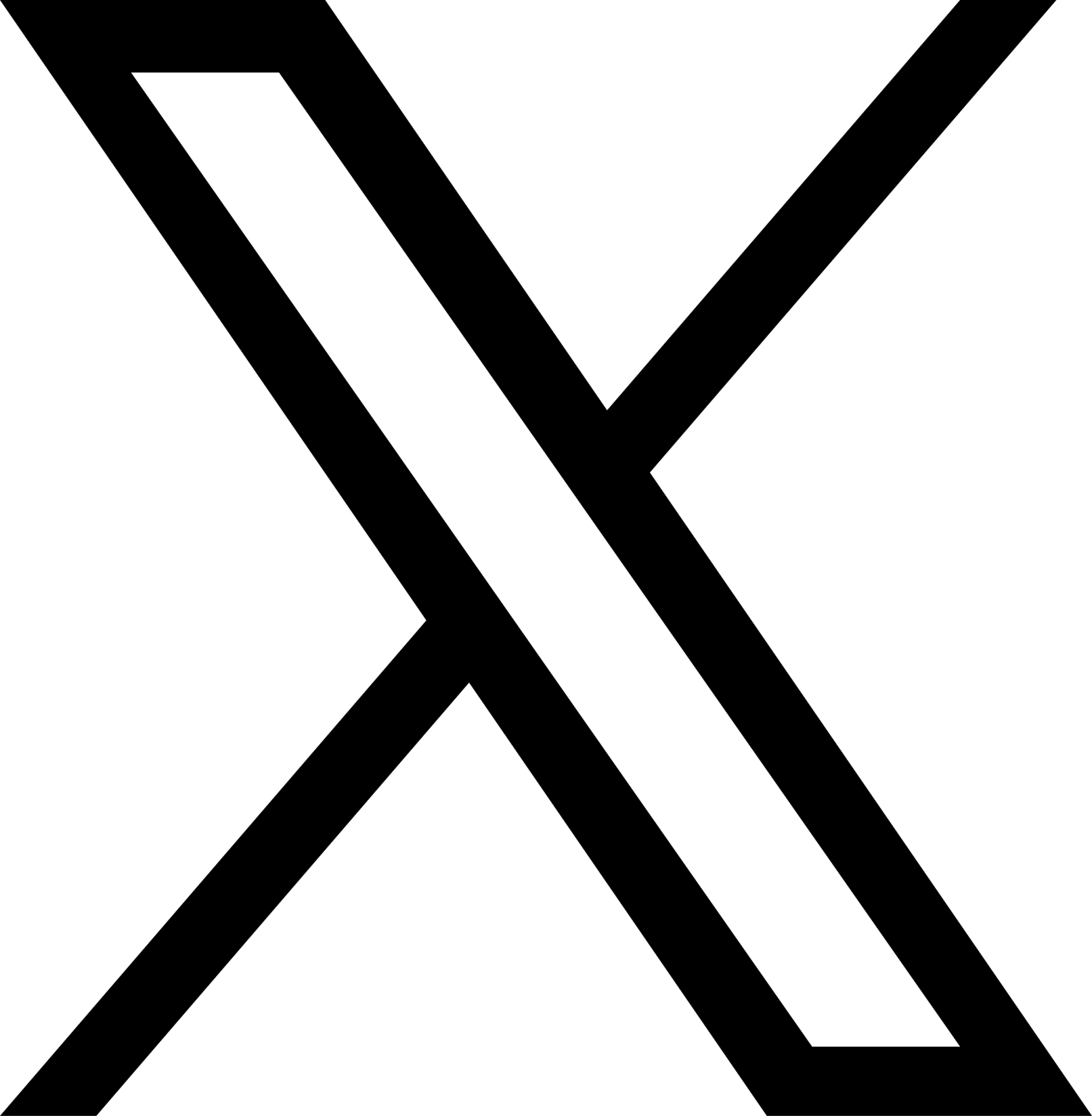
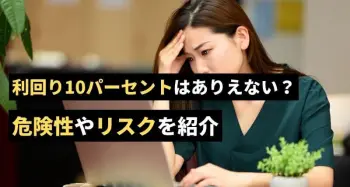
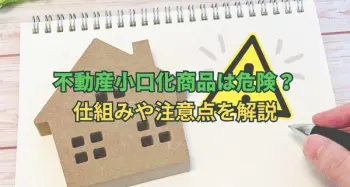
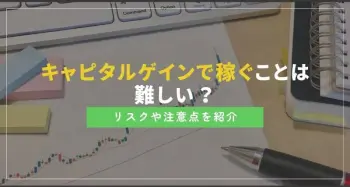
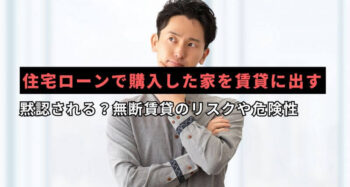
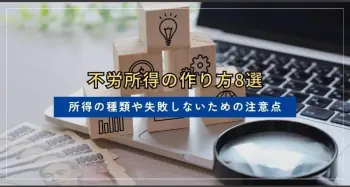

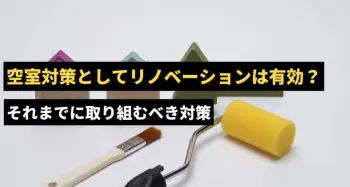
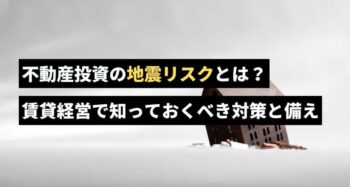

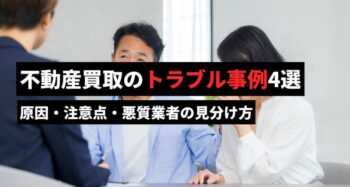
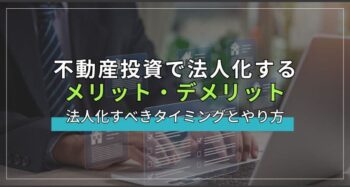
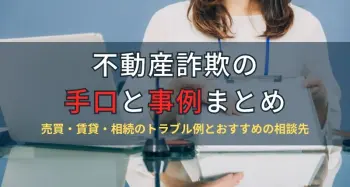
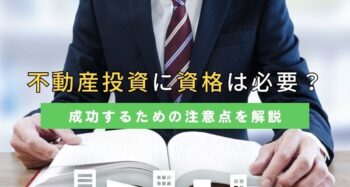
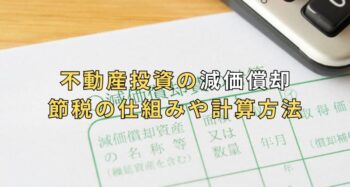
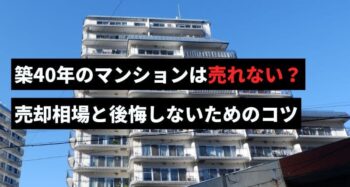
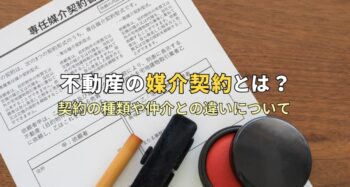
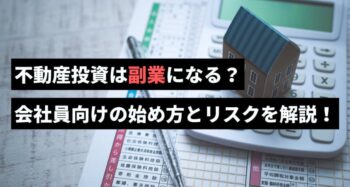
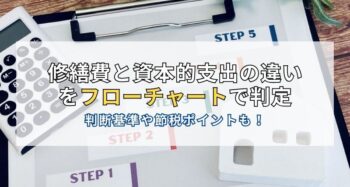
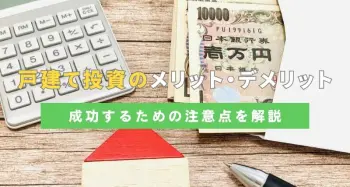
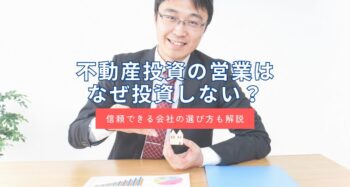
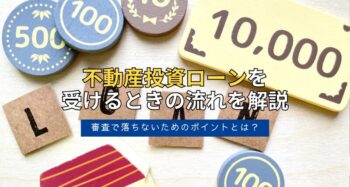
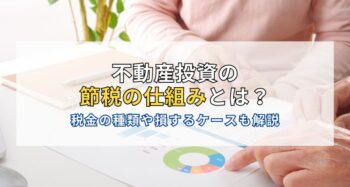

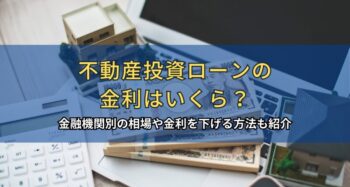
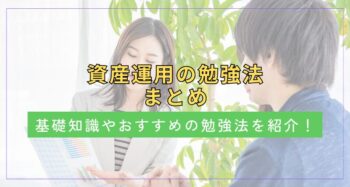



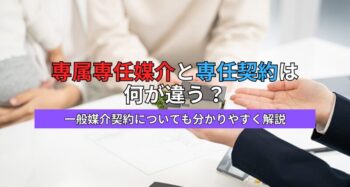

マンション投資に関するお問い合わせはこちら