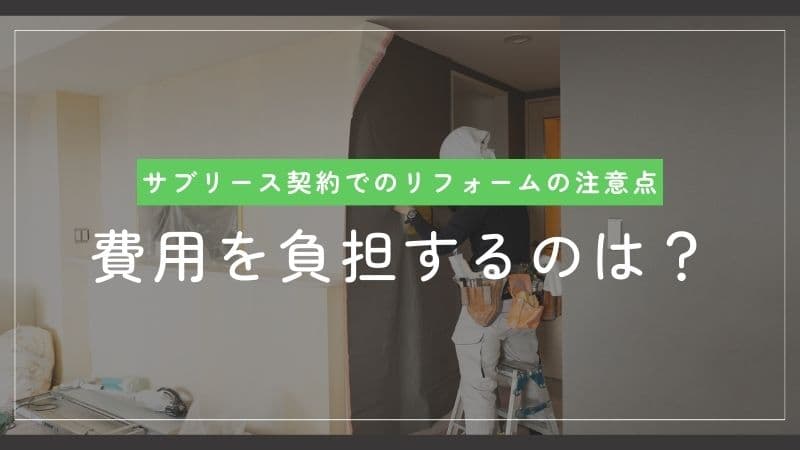
サブリース契約ではリフォームの費用はオーナーが負担することになり、金額によってはローンを組む必要があるかもしれません。サブリース契約でリフォームをするときに、どういったことに気をつければよいのかを解説します。
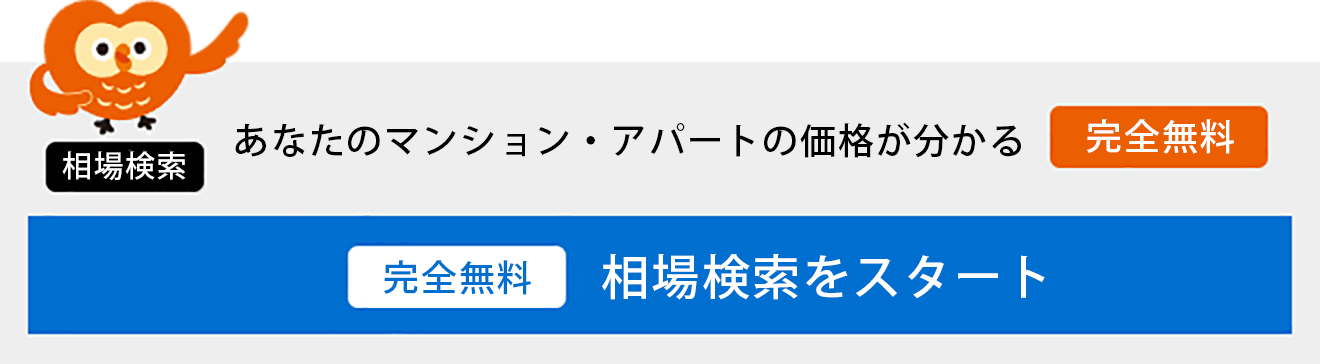
サブリース契約でのリフォーム費用はだれが負担する?
サブリース契約では、一般的にリフォームはサブリース会社が主導して行います。
オーナーの負担がなく安心だと思うかもしれませんが、実は思いもよらない落とし穴があります。今から詳しく解説します。
原則、リフォーム費用を負担するのはオーナー
契約内容によりますが、一般的にサブリース契約ではリフォーム費用を負担するのはオーナーです。
サブリースの契約書には、サブリース会社が負担する修繕の内容が書かれています。簡易的な修繕はサブリース会社が負担し、経年劣化分など大掛かりなものはオーナーが負担するパターンが多いです。
そのため、オーナーに高額な料金が請求される場合があります。
サブリース契約だからといって安心せず、リフォーム費用を組み込んだシミュレーションをしておかないと、想像していた以上の負担を強いられます。
サブリース契約をする際は、契約書の内容をしっかり確認しましょう。
リフォーム費用負担の内容
サブリース会社がリフォームを主導してくれるとはいえ、費用を負担するのはオーナーなので、どのようなリフォームが行われるのか内容を理解しておくことも大事です。
具体的には下記のようなリフォームがあります。
| リフォームの種類 |
内容 |
| 原状回復工事 |
入居者が退去したあとに、部屋を元の状態に戻す修繕
(ハウスクリーニング、壁紙の張り替えなど) |
| 補修 |
オーナー負担で行われる修繕
(雨漏り、水回りの経年劣化など) |
| 予防修繕 |
修理が必要になる前に予防的に行われる修繕
(外壁のひび補修、など) |
| 大規模修繕 |
経年劣化の対応として行われる修繕
(防水工事など) |
費用は原状回復工事なら数万円〜数十万円程度ですが、防水工事などの大規模修繕になると数百万円にもなります。
そのため修繕費用を用意しておかなければ、修繕のためにローンを組む必要がでてくるかもしれません。
大規模修繕は多くの場合12年に1度行われるので、計画的に予算を積み立てておくことが大事です。
サブリースで発生する具体的なリフォームの種類と費用感
プロも驚くサブリースでの法外なリフォーム費用の事例
リフォームの透明性の確保が重要
実際にリフォームが行われる際は、リフォーム内容や費用をしっかり確認することが大事です。確認を怠ると、下記のようなことが起こる可能性があります。
- 法外な費用を請求され、余計な出費がかさむ
- 不必要なリフォームが実施され、工事費を中抜きされる
このような事態を防ぐためにも、相見積もりなどで相場を確認しておくことが重要です。
また、中抜きを防ぐために実際にかかった費用は確認しましょう。
サブリースにおけるリフォームトラブルは多い
リフォームの内容や費用の妥当性判断するには?
サブリースのリフォームにおける注意点
サブリース契約でリフォームする際の注意点を紹介します。
事前にしっかりと契約内容を確認する
サブリース契約でリフォームする際に最も重要なことは、しっかりと契約内容を確認することです。特に費用負担に関しては、よく確認しておきましょう。
確認せずに契約してしまうと、思いがけない出費で困ることになりかねません。
そのうえでリフォームを実施する際にも、内容をきちんと確認することでトラブルを未然に防げます。
またリフォームの賃貸収入への影響や保証内容など、分からないことがあれば契約前に質問し、納得したうえで契約することが大切です。
契約の段階で信頼できるサブリース会社を選ぶ
もう一つの注意点は、信頼できるサブリース会社と契約を結ぶことです。信頼できる会社であれば、トラブルも少なく賃貸運営できます。
契約前のやり取りで判断するだけでなく、全日本不動産協会や全国宅地建物取引業協会に加盟しているかなども確認しておきましょう。
たとえば「全日本不動産協会」は、宅地建物取引業の健全な発展を目指し住宅や土地関連の政策提言などを行う協会で、2013年からは内閣総理大臣認定の公益社団法人として活動しています。
サブリース契約は長い付き合いになります。しっかりと信頼できる会社を選ぶようにしましょう。
信頼できるサブリース会社を見分けるチェックポイント
リフォーム以外で発生するサブリース費用
サブリース契約ではリフォーム以外にも、下記のような費用が発生します。
それぞれ詳しく解説します。
不動産会社に支払う手数料は管理委託よりも高い
サブリース契約は通常、家賃保証がありオーナーが受け取る賃料は、満室時の80〜90%が相場です。
賃料から保証料を差し引いた分が不動産会社に支払う手数料であり、賃料の10〜20%が相場です。
管理委託での手数料の相場が5%程度であることに比べて、高いと感じるかもしれません。
ただし管理委託には家賃保証がなく、サブリースと管理委託どちらにメリットがあるかは一概にはいえません。立地条件や契約内容などにより異なります。そのため、慎重に検討する必要があります。
共用部のメンテナンス費用もオーナーが負担する
また共用部のメンテナンス費用も、オーナーが負担するケースが多いです。たとえば、共用部の清掃や電気代、雑草の処理などです。
ただし共用部のメンテナンス費用は手数料に含まれている場合もあります。契約書をしっかり確認しておきましょう。
サブリースの費用負担が重いと感じたら、売却も検討する
サブリースの費用負担が重いと感じたなら、物件を売却してしまうのも1つの選択肢です。
売却することで、高額な修繕費の負担や将来的な家賃保証の減額などのリスクを回避できます。また、まとまった資金を手元に用意できます。
物件の維持管理に負担を感じたなら、売却も検討してみてください。
サブリースは解約できる?
サブリースの物件を売る場合、サブリース契約の解約後のほうが買主を見つけやすいはずです。しかし、結論からいえば、サブリースの解約は難しいでしょう。
サブリース契約は「借地借家法」適用内の法律であり、借地借家法では借主(不動産会社)が貸主より手厚く守られます。サブリースの場合、借主には不動産会社が当てはまります。
また解約できても、高額な違約金が発生することもあるんです。
契約する前に、契約書の解約についての内容も確認しておきましょう。もし解約ができない場合は、サブリース契約のまま売却することもできます。
売却の流れ
サブリース物件を売却する際の流れは、サブリースを解約できるかで変わります。
解約できる場合は、サブリース契約を解約した後に売却します。
ただしすぐに売れるとは限らないので、不動産会社に買い手を探してもらいつつ、サブリース会社にも話しを通しておくことが得策です。買い手が見つかれば、売却とタイミングを合わせてサブリース契約も解約することで安心して売却できます。
解約できなければ、サブリース契約を引き継いだまま売却します。購入者が決まれば、売主・買主・サブリース会社で契約内容を継承する合意書を作成します。
また、サブリース契約のまま売却すると、利回りが悪くなるなどの理由から売れにくくなる点がデメリットです。
売れなかった場合も費用が発生する?
物件が売れなかった場合は費用は一切発生しません。広告費などは売却した際に発生する仲介手数料に含まれます。
サブリース物件を高く売るなら不動産会社選びが重要
サブリース物件の売却は、不動産会社選びが重要です。サブリース物件の取引経験が豊富な会社なら、取引をスムーズに行えるからです。
経験の少ない不動産会社を選んでしまうと、解約交渉などでトラブルが起こるかもしれません。
サブリース物件の売却は複雑です。取引に慣れた不動産会社を選ぶことで安心して任せることができるうえに、物件を高く売ることにもつながります。
サブリース物件を高く売るなら、取引に慣れた不動産会社を選ぶようにしましょう。
オーナーが意外と知らない、リフォーム以外の費用
サブリース契約の費用負担が重いと感じた場合の選択肢
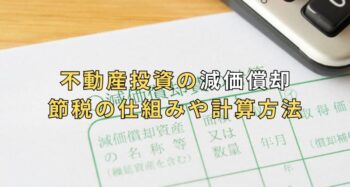




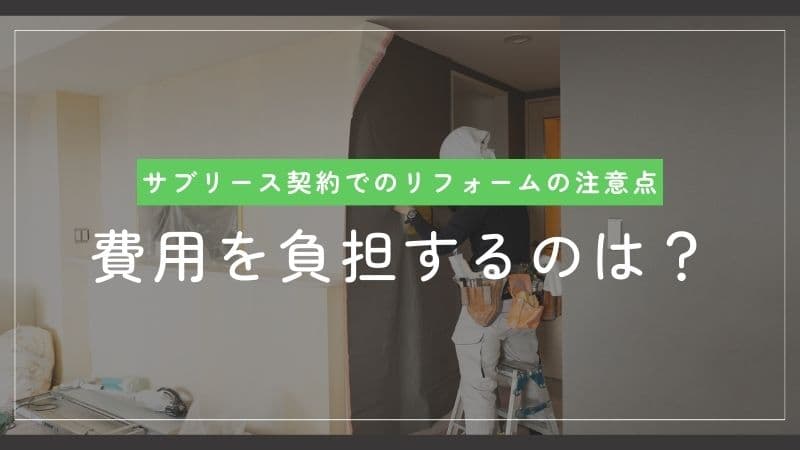
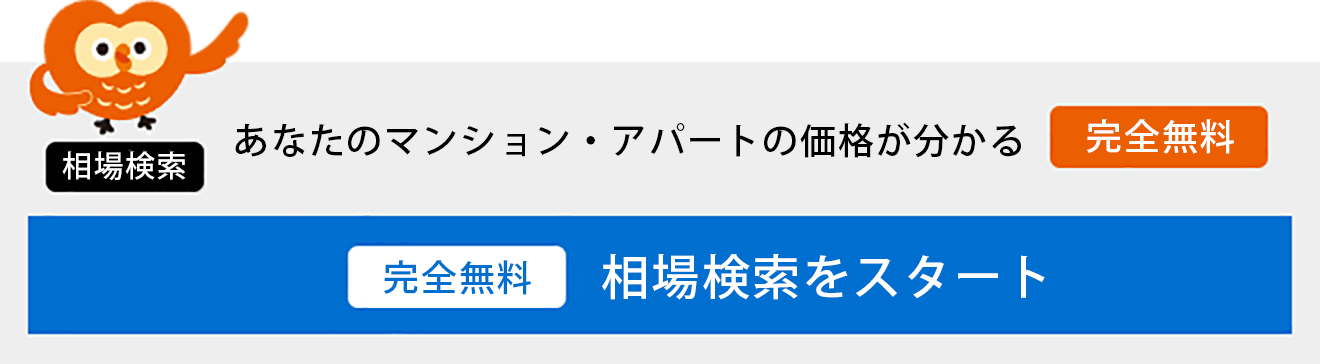



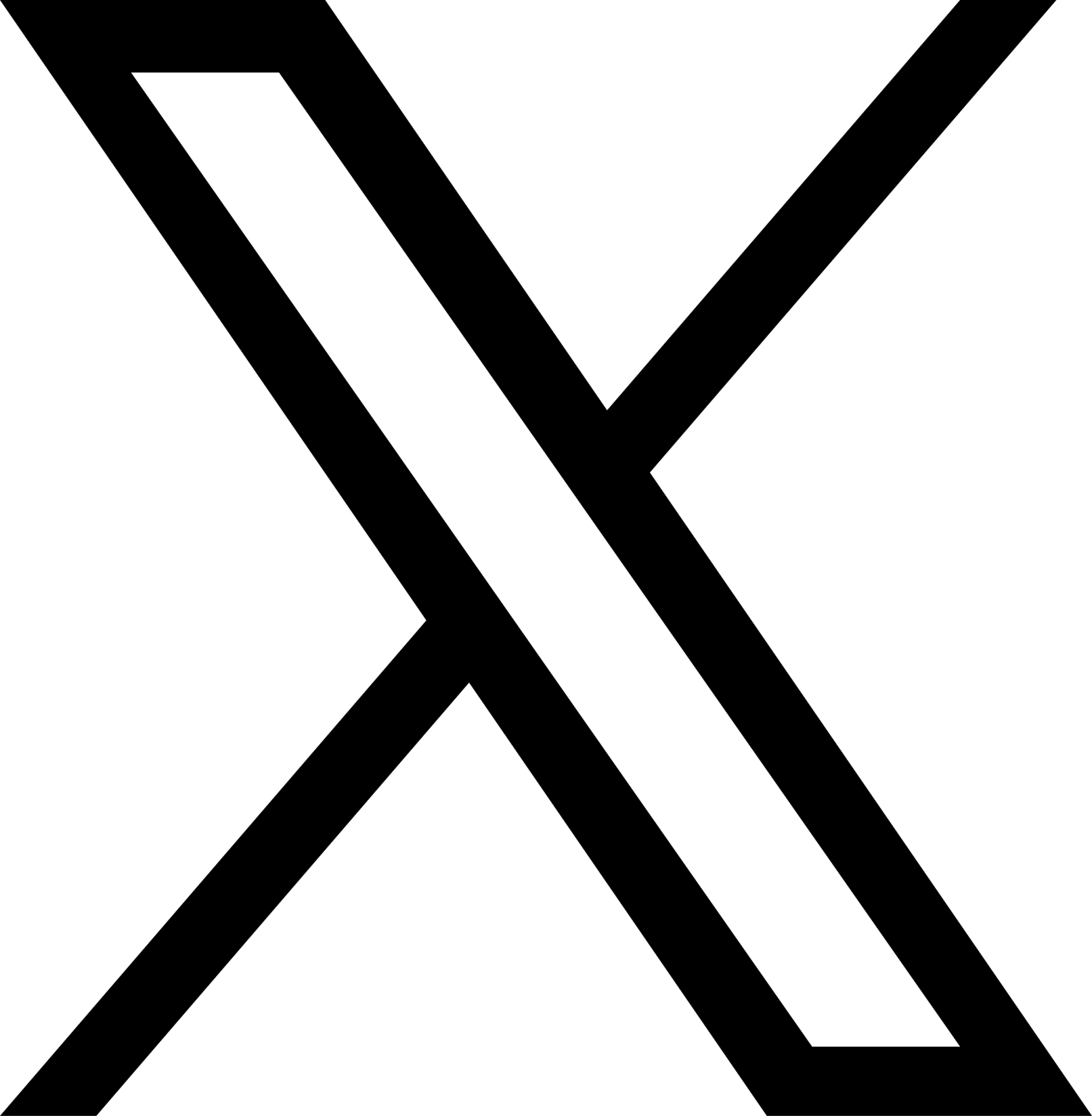
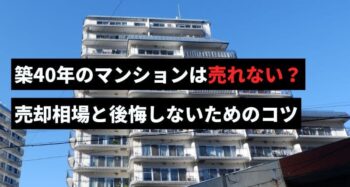
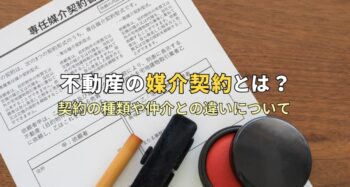
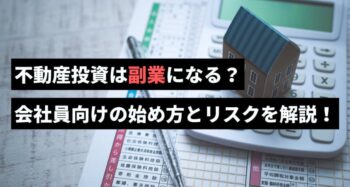
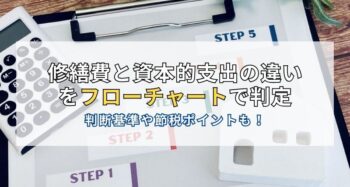
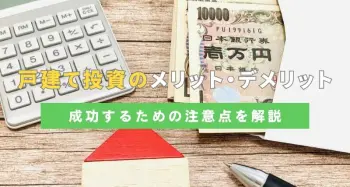
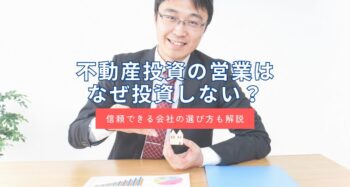
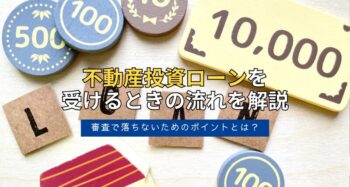
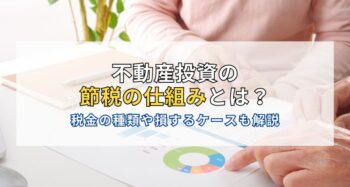

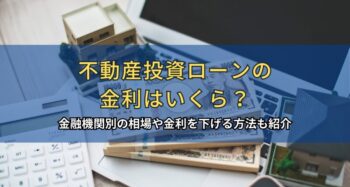
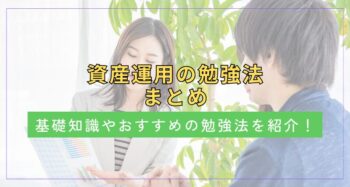



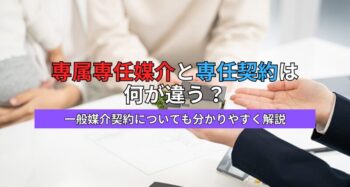
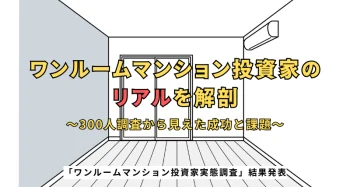
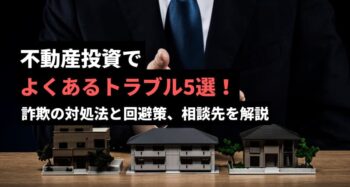
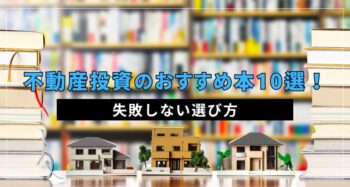
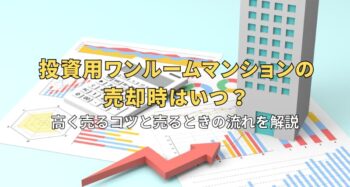

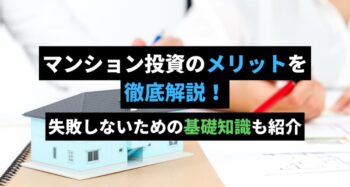

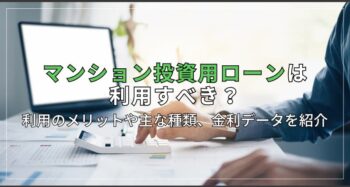

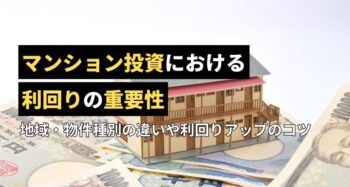

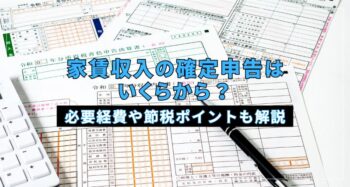
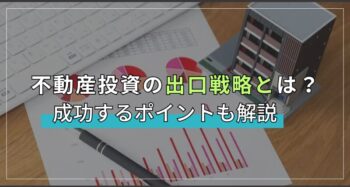
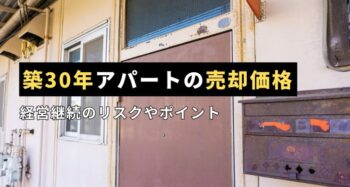

代表取締役伊藤幸弘
サブリース契約で発生するリフォームは、主に現状回復工事を指します。これは退去者が出た後に、室内を入居可能な状態に戻すための工事のことです。ワンルームマンションや40㎡以下の投資用マンションでは、平均入居期間が約3年となっているため、3年ごとに入居者の入れ替わりが発生し、その都度現状回復工事が必要になります。
現在のリフォーム費用は高騰しており、投資を行っている立場からすると非常に厳しい状況です。具体的な費用感をご紹介すると、20㎡程度のワンルームマンションの場合、クロス(壁紙)の交換で約20万円前後、フローリングの張り替えで20~30万円程度かかります。さらにハウスクリーニング費用として3万~4万円程度が必要となり、これらが基本的な現状回復工事の費用となります。
築年数が経過した物件では、水回り設備の交換が必要になることもあり、この場合は数百万円規模の費用が発生することもあります。また、エアコンや給湯器などの設備機器の故障や老朽化による交換も、すべてオーナーの負担となります。
サブリース業者は借主としての立場から、「入居に支障をきたす状態なので修繕してください」という正当な要求を行うことができます。これは入居者募集や物件の競争力維持の観点から必要な工事であり、オーナーとしては避けて通れない費用と考える必要があります。