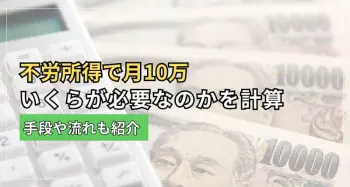
投資マンション成功
不労所得の作り方8選。所得の種類や失敗しないための注意点

働かずに収入を得る「不労所得」に注目が集まっています。人生100年時代において、労働収入だけでは将来への不安が尽きません。本記事では、初心者でも始めやすい不労所得の作り方を詳しく解説し、失敗しないための注意点もお伝えします。
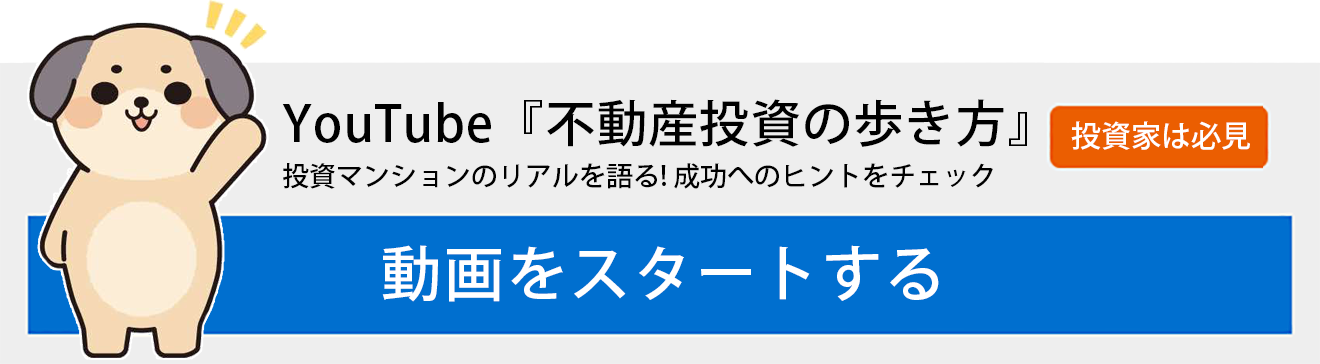
目次
不労所得とは?基本概念を理解しよう
働き続けることができる期間と実際に生活に必要な期間は同じではありません。特に65歳から70歳、もしくは75歳までの収入空白期間への対策として、不労所得への関心が急速に高まっているのです。
まずは、不労所得についてわかりやすく解説します。
不労所得の定義と仕組み
不労所得とは、自分で労働することなく得られる収入のことを指します。株式の配当金や不動産の家賃収入、ブログからのアフィリエイト収入などが代表的な不労所得です。しかし、何もしないで得られる収入ではなく、事前に収入を得るための準備や初期投資が必要です。
不労所得の「不労」とは、収益が安定して発生している状況を指しています。株式投資であれば事前の勉強や分析、不動産投資であれば物件の選定や管理会社との関係構築など、利益を得るには事前に相当な労力が必要となります。
労働所得との違い
労働所得は労働したことによる対価をお金に交換する仕組みです。働いた時間に応じて給与が決まり、働かなければ収入はありません。一方、不労所得は一度仕組みが完成すれば、基本的に継続して収入を生み出すことが可能です。
両者の違いは収入の上限も挙げられます。労働所得では1日24時間という物理的な制約がありますが、不労所得では時間の制約を超えて収益を得ることが可能です。
不労所得の種類
不労所得は大きく分けて2つのタイプに分類されます。それぞれ特徴が異なるため、目的に応じて選択することが重要です。
インカムゲイン型(継続収入)
インカムゲイン型は、資産を保有することで定期的に収入を得る仕組みです。株式の配当金、不動産の家賃収入、債券の利息などがこれに該当します。比較的安定した収入が期待できる一方で、大きなリターンは期待しにくいという特徴があります。
長期的な資産形成や老後の生活費確保を目的とする場合に適しており、リスクを抑えながら安定収入を求める投資家に人気があります。
キャピタルゲイン型(売却益)
キャピタルゲイン型は、資産の価格上昇による売却益を狙う仕組みです。株式や不動産の値上がり益、仮想通貨の価格上昇などが代表例です。短期間で大きな利益を得られる可能性がある反面、価格下落により多額の損失が発生するリスクがあります。
リスクがあっても高いリターンを狙いたい投資家や、ある程度の資金的余裕がある場合に検討される投資手法です。
- 投資マンション相場検索 高値売却はこちら
- 0120-109-998
-
10:00~19:00((年末年始除く))

【初心者向け】おすすめの不労所得の作り方8選
ここからは、初心者でも比較的始めやすい不労所得の作り方を8つ紹介します。それぞれの特徴や注意点を理解して、自分に合った方法を選択することが成功への第一歩です。
1. 投資信託・ETF(月1万円から開始可能)
投資信託・ETF(上場投資信託)は、少額から始められる代表的な不労所得の手段です。金融庁が公表しているNISAの利用状況に関する調査結果では、2025年6月末の時点では2024年12月末から利用率が平均5.4%増加しており、10代においては28.5%の増加率です。
分散投資のメリット
投資信託の最大のメリットは分散投資です。1つのファンドで数百から数千の銘柄に投資できるため、個別の株投資に比べてリスクを抑えられます。たとえば、2024年からスタートした新NISAでは年間投資枠が最大360万円に拡大され、非課税での資産形成が可能となりました。
新NISAは日本国内に住んでいる18歳以上の方であれば誰でも開設できるので、投資初心者の方でも気軽に始められます。
参考:金融庁「NISAを知る:NISA特設ウェブサイト」
おすすめの投資信託の選び方
初心者におすすめなのは、低コストのインデックスファンドです。新NISAのつみたて投資枠では「日本を含む全世界株式の投資信託」を利用することができます。
信託報酬(運用手数料)が年0.1%台の低コストファンドを選び、長期的な資産形成を心がけることが重要です。
2. 株式投資(配当金・株主優待)
株式投資による配当金は、企業の利益の一部を株主に還元する仕組みです。日本の上場企業の多くが年2回の配当を実施しており、配当利回りが3〜5%程度の銘柄も存在します。
高配当株の選び方と注意点
高配当株を選ぶ際は、配当利回りだけでなく企業の財政や事業の持続性を確認することが重要です。配当性向(利益に対する配当の割合)が適正範囲内であること、継続的に利益を上げていることを確認しましょう。
また、一時的な高配当に惑わされず、過去数年間の配当実績や将来の配当方針を確認し、総合的に判断することが必要です。
株主優待を活用した生活費削減
株主優待は日本特有の制度で、企業が株主に対して自社製品やサービスを提供するものです。食品会社の商品や小売業の割引券など、生活に密着した優待を活用することで、実質的な生活費削減効果が見込めます。
ただし、優待目的だけで投資をするのではなく、企業の成長性も考慮した総合的な投資判断が大切です。
3. 不動産投資(家賃収入)
不動産投資は安定した収入を得られる可能性がある投資手法です。物件価格の上昇によるキャピタルゲインも期待できますが、初期投資額が大きく、空室リスクや修繕費用などの管理コストも考慮する必要があります。
区分マンション投資の基本
ワンルームマンション投資は、マンションの1室から始められる比較的ハードルの低い不動産投資です。新築か中古かの選択、立地条件の見極め、管理会社の選定など、多くの要素を検討するために不動産の知識も必要になります。
投資用ローンを活用する場合は、金利上昇リスクや返済負担の比率を計算し、キャッシュフローがプラスになることを確認しましょう。
不動産クラウドファンディング
近年注目されているのが不動産クラウドファンディングです。1万円程度で不動産投資に参加でき、物件管理の手間も不要なので気軽に始められるでしょう。ただし、元本保証はないため、運営会社の信頼性を十分に調査することが重要です。
4. ブログ・アフィリエイト運営
ブログやアフィリエイトは、初期費用を抑えて始められる不労所得の方法です。サーバー代やドメイン費用を合わせても年間1〜2万円程度で開始できるため、学生や若年層にも人気があります。
収益化までの期間と現実的な収入
ブログで収益化するまでには通常6カ月から1年程度の期間が必要です。初期段階では記事の執筆に多くの時間を費やすことになり、SEO対策やマーケティングについても学習する必要があります。
現実的な収入としては、月1〜3万円程度を最初の目標とするとよいでしょう。月10万円以上の収入を得るには、相当な時間と努力が必要になります。
継続のコツとジャンル選定
ブログを継続するためには、自分の興味や専門知識がある分野を選ぶことが重要です。また、市場規模が十分にあり、アフィリエイト案件が豊富なジャンルを選択することで、収益化の可能性を高められます。
定期的な更新スケジュールを設定し、読者のニーズに応える質の高いコンテンツを提供し続けることが成功の鍵です。
5. 写真・動画の素材販売
近年はデジタル技術の普及により、写真や動画素材の需要が高まっています。趣味で撮影している写真や動画を素材として販売することで、継続的な収入を得ることが可能です。
ストックフォトサイトの活用法
ShutterstockやAdobe Stockなど大手ストックフォトサイトに作品を登録することで、世界中の購入者に作品を販売できます。季節性のある風景写真、ビジネスシーンの人物写真、料理写真などは需要が高い傾向です。
ただし、収益化には数多くの作品が必要になり、月数千円程度の収入を得るには数百点の作品が必要になることが一般的です。
6. 電子書籍出版(Kindle)
電子書籍出版は、個人でも簡単に始められる出版方法です。専門知識や体験談を書籍化することで、長期的な印税収入を得ることができます。
出版から収益化までの流れ
Kindle Direct Publishing(KDP)を利用すれば、原稿の準備から出版まで無料で行えます。表紙デザインや編集作業も自分で行うことで、コストを最小限に抑えることが可能です。
35%のロイヤリティオプションと 70%のロイヤリティオプションがあり、利益を得るにはそれぞれ要件が設定されています。継続的な売上を維持するためには、マーケティングや読者レビューの獲得にも意識して作成する必要があります。
参考:Amazon Kindle「電子書籍のロイヤリティ オプション」
7. 駐車場経営・土地活用
遊休地を活用した駐車場経営は、比較的手堅い不労所得の方法です。コインパーキングとして運営するか、月極駐車場として貸し出すかで収益構造が異なります。
初期投資にかかるのは土地の舗装や精算機の設置費用程度なので、不動産投資に比べて参入ハードルが低いのが特徴です。ただし、立地条件によって収益性が大きく左右されるため、周辺の駐車場需要を十分に調査することが重要です。
8. シェアリングビジネス(民泊・カーシェア)
シェアリングエコノミーの発展により、個人でも民泊やカーシェアビジネスを始めることができるようになりました。既存の資産を活用して収入を得られるため、投資の費用を抑えながら不労所得を構築できます。
民泊の場合は、旅館業法の許可や近隣住民への配慮、清掃やゲスト対応などの運営面での検討が必要です。カーシェアの場合は、車両の維持管理費用と利用料収入のバランスを慎重に計算することが重要です。
マンション投資に関するお問い合わせはこちら
- 投資マンション相場検索 高値売却はこちら
- 0120-109-998
-
10:00~19:00((年末年始除く))

初心者が陥りやすい不労所得でよくある失敗パターン4選
不労所得では多くの初心者が陥りやすい失敗例があります。これらの失敗事例を事前に理解し、適切な対策を行うことで、成功確率を大幅に向上させることができます。
短期間で大きな利益を期待する
「3カ月で月収50万円」といった誇大広告に惑わされ、現実的でない期待を抱く人が後を絶ちません。実際には、安定した不労所得の構築には年単位の時間が必要です。
そのため、半年や1年間など適切な期待値を設定することが重要です。投資には必ずリスクが伴うことを理解し、失っても生活に支障のない余裕資金での投資を心がけましょう。
一つの方法に依存しすぎる
一つの投資方法に依存することは、大きなリスクを伴います。市場環境の変化や法的規制の変更により、その方法が機能しなくなる可能性があるためです。複数の収入源を組み合わせることで、リスクの分散を図ることが重要です。
高額教材を販売するセミナーを利用する
「秘密の投資手法を教えます」として高額な教材やセミナーを販売する業者にも注意が必要です。本当に有効な投資手法であれば、わざわざ他人に教える人はいないでしょう。
投資の学習は、書籍やインターネットの無料情報、金融機関の公式資料から始めることが安全で効果的です。
会社の規定に違反していた
会社員の場合、勤務先の副業規定を確認することが重要です。投資による不労所得は一般的に副業には該当しませんが、ブログ運営や不動産業務など、積極的な事業活動が伴う場合は注意が必要です。
不明な点がある場合は、人事部門への事前相談や、税理士へ相談をしてみましょう。
マンション投資に関するお問い合わせはこちら
- 投資マンション相場検索 高値売却はこちら
- 0120-109-998
-
10:00~19:00((年末年始除く))

不労所得で成功するためのポイント
失敗を避けるだけでなく、成功に向けた積極的な心構えを持つことが、不労所得構築の成功確率を高めます。最後に、不労所得で成功するための方法をご紹介します。
長期的な視点を持つ
不労所得は短期的な成果を求めるものではなく、長期的な資産形成の手段です。市場の一時的な変動に一喜一憂せず、10年、20年という長期スパンで資産形成を考えることが重要です。
特に投資信託やETFへの積立投資では、時間の分散効果によりリスクを軽減できるため、長期継続することが重要です。
少額から始めて徐々に拡大
最初から高額を投資するのではなく、小額から始めて経験を積むことが重要です。目標設定として月1〜3万円を稼ぐことを目標にして、段階的に投資額や目標金額を引き上げていくとよいでしょう。
必要に応じて確定申告をする
会社員の場合、給与以外の所得が年間20万円を超える場合は確定申告が必要です。配当金、家賃収入、アフィリエイト収入など、様々な不労所得が対象となります。
NISA口座での投資益は非課税ですが、特定口座や一般口座での投資益には税金がかかります。税務処理を簡素化するため、特定口座(源泉徴収あり)の利用を検討することも有効です。
継続的な学習と改善
金融市場や投資環境は常に変化するため、継続的な学習が不可欠です。定期的に投資成績を見直し、改善点を見つけて戦略を修正することで、より良い結果を得ることができます。
不労所得は一朝一夕でできることではありません。適切な知識とリスクを理解し、自分に適した方法を選択して、着実に資産形成を進めていきましょう。
あなたのマンション・アパートの価格が分かる
コラム監修

伊藤 幸弘(いとう ゆきひろ)
株式会社TOCHU(トウチュウ)代表取締役
投資マンション専門家/不動産コンサルタント
プロフィール
2002年より投資用中古ワンルームマンション売買のキャリアをスタートし、現場での売主・買主双方のリアルな課題解決を通じて、個人投資家の資産形成支援に従事。
2014年に株式会社東・仲(現:株式会社TOCHU)を立ち上げ、通算の取扱実績は20,000件以上。
2025年からは業界初の価格透明化サービス「TOCHU iBuyer」を展開し、中古投資マンション市場の健全化を推進。
「誠実な取引こそが市場の信頼をつくる」という理念のもと、投資マンションの適正な価値形成を目指して活動している。
保有資格
・公認 不動産コンサルティングマスター
・宅地建物取引士
・ファイナンシャル・プランニング技能士
・賃貸不動産経営管理士
・投資不動産取引士
・競売不動産取扱主任者
・日本不動産仲裁機構 認定ADR調停人
著書・実績
『投資ワンルームマンションをはじめて売却する方に必ず読んでほしい成功法則』(クロスメディア・パブリッシング)
『マンション投資IQアップの法則 〜なんとなく投資用マンションを所有している君へ〜』(CHICORA BOOKS)




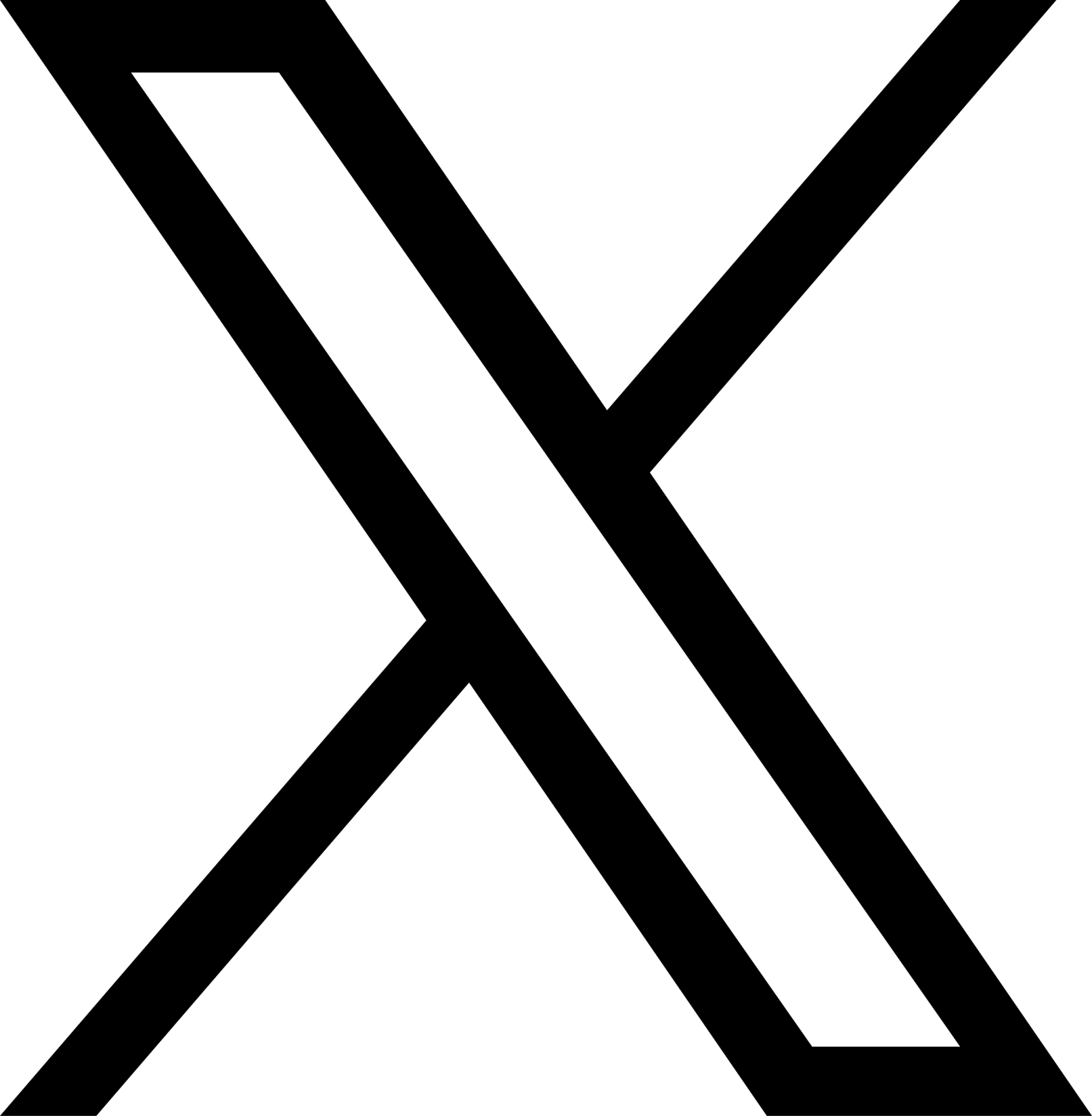
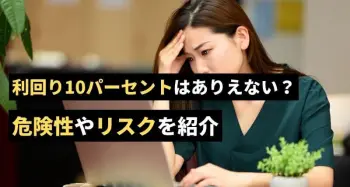
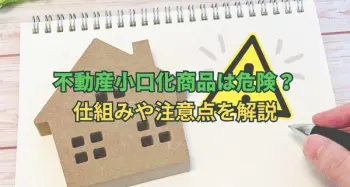
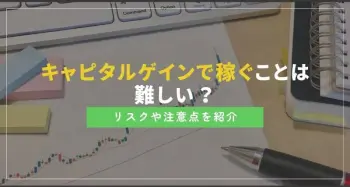
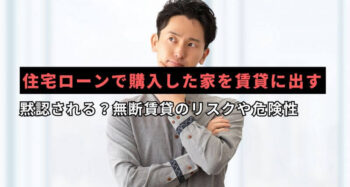
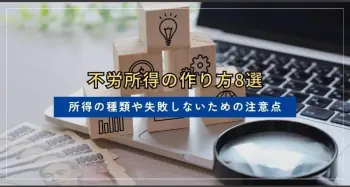

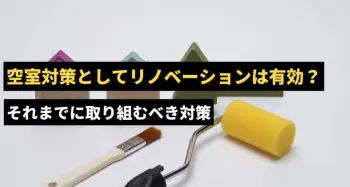
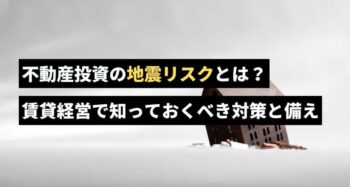

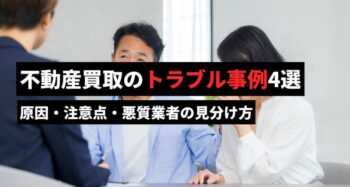
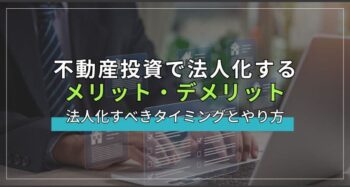
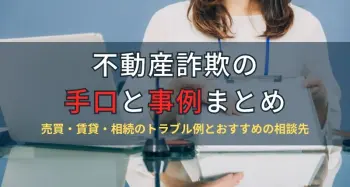
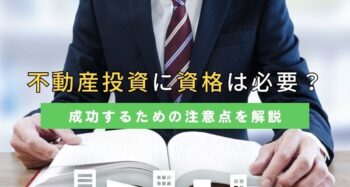
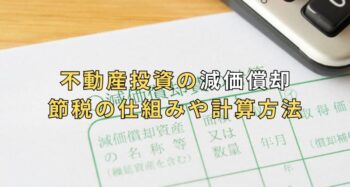
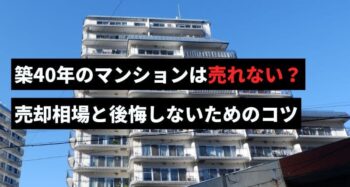
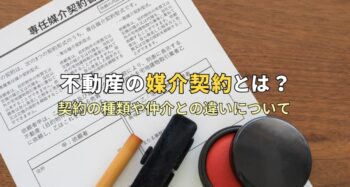
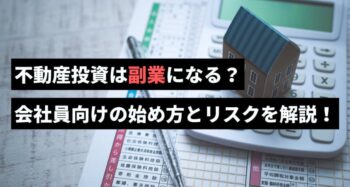
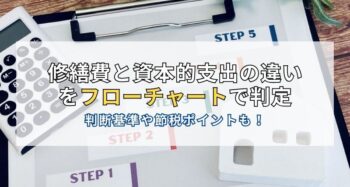
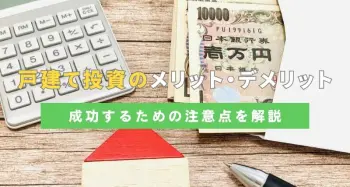
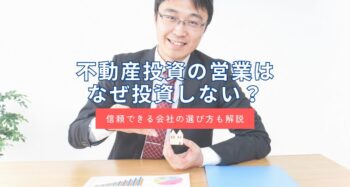
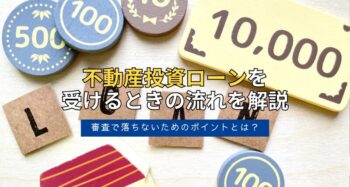
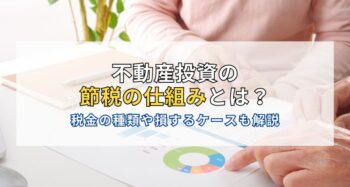

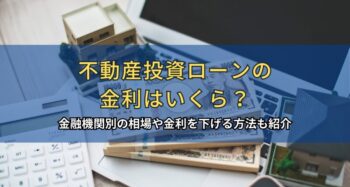
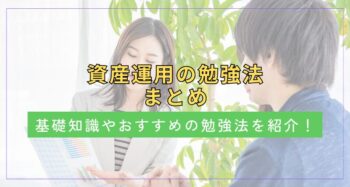



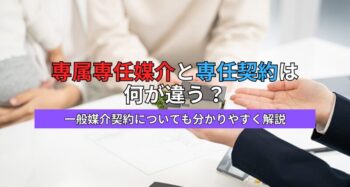

マンション投資に関するお問い合わせはこちら